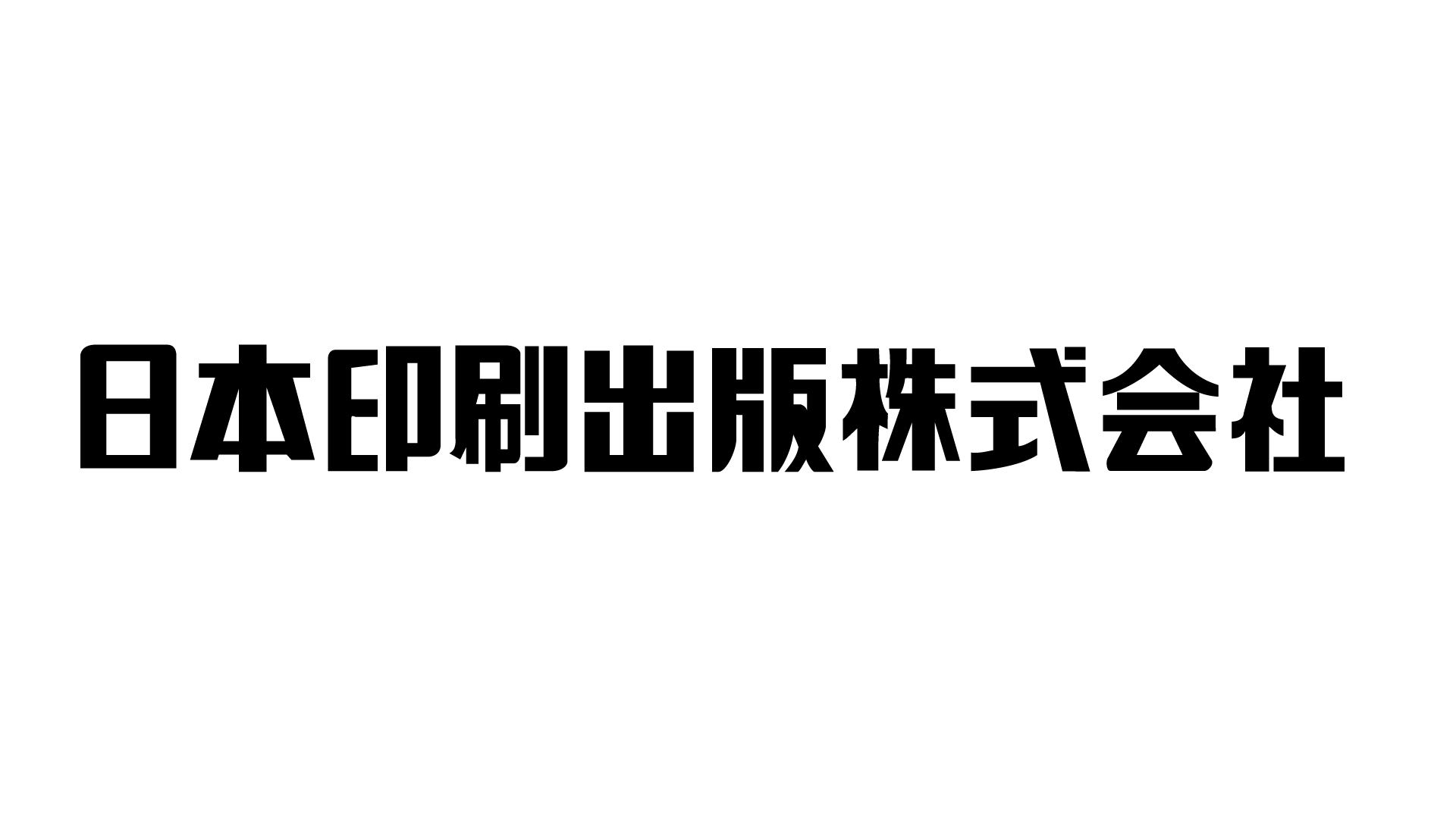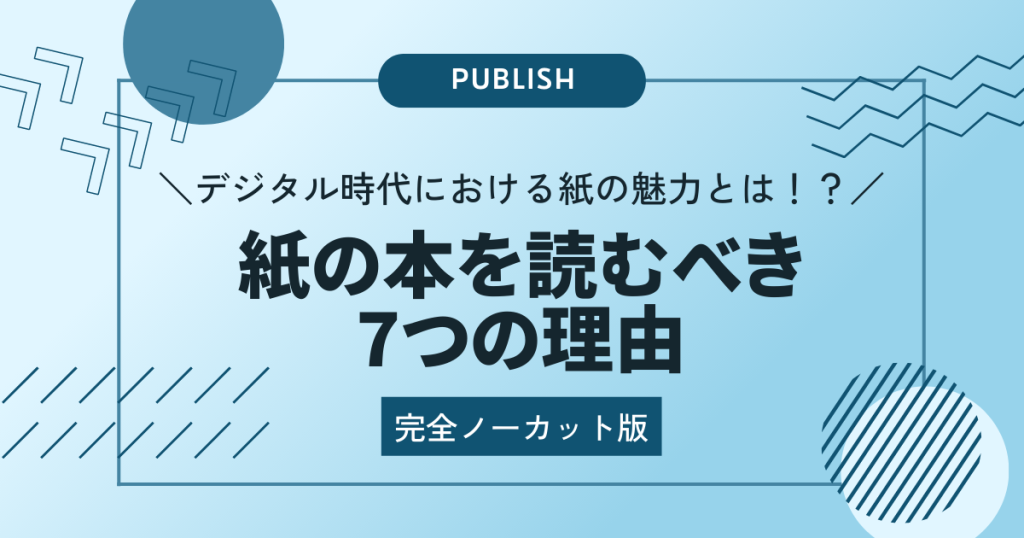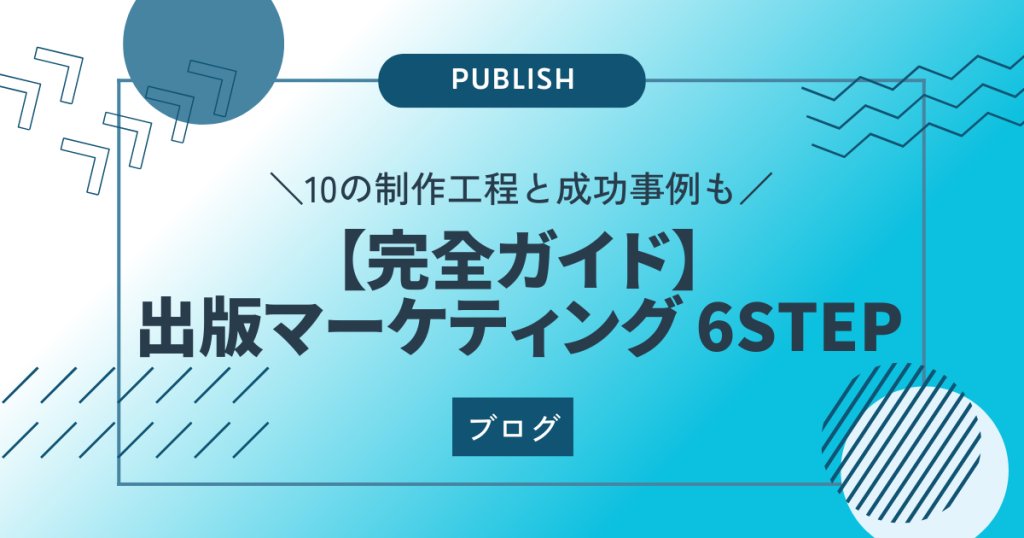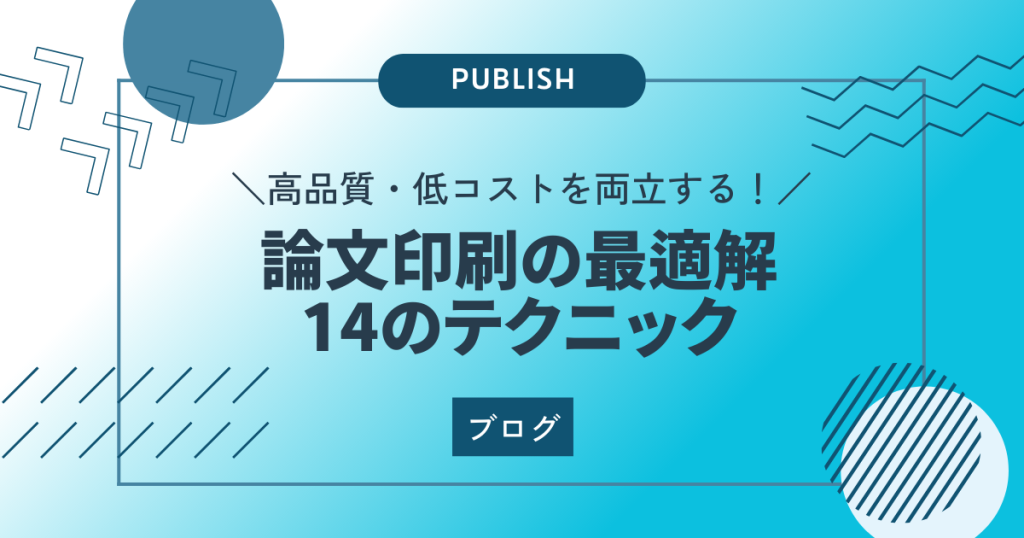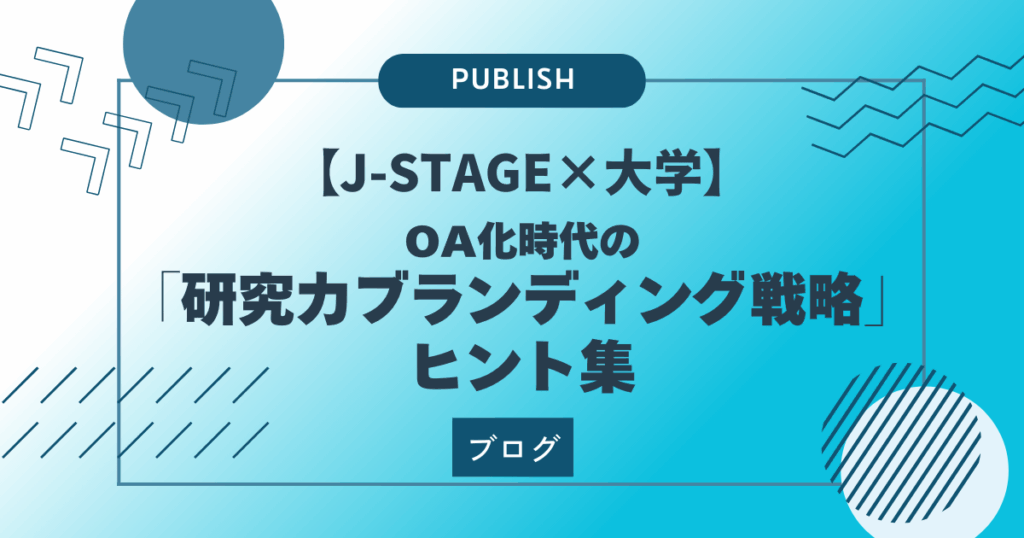
「大学の紀要、もっと広く読まれるにはどうすればいい?」
「研究成果を効果的に発信する方法は?」
そんな疑問を抱える大学関係者に向けて、本記事ではJ-STAGEの価値について解説します。
導入によるメリットや注意点、運用ステップ、そして大学の注目事例までを網羅。
J-STAGEを単なる論文公開ツールにとどめず、「研究ブランディング戦略」として活かすヒントが満載です。
※本文中の説明はすべて2025年4月現在の情報に基づきます。
第1章|J-STAGEとは何か?大学にとっての価値を再定義する
まずはJ-STAGEの基本概念と、大学における利用価値について理解を深めていきましょう。

1-1. J-STAGEの概要──なぜ「大学」で注目されているのか
J-STAGEは、国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)が運営する電子ジャーナルプラットフォームです。日本の学会や研究機関の発行物をデジタル化し、1999年から国内外へ広く公開しています。
大学では特に、学内紀要や研究報告書の公開手段として注目されています。学会や研究者だけでなく、企業や個人も無料で利用できる点が、最大の魅力です。
1-2. オープンアクセス時代の「研究発信インフラ」としての位置づけ
近年、論文は「オープンアクセス」(インターネット上で誰もが制限なく無料で利用できる仕組み、以下「OA」)で公開するのが主流となっています。2025年からは、科研費などの公的資金活用による研究成果は、学術雑誌に掲載後、即時に公開することが義務化されました。
こうした背景からも、国内最大級のプラットフォームであるJ-STAGEは、OA時代の日本における研究発信インフラの筆頭に位置づけられるでしょう。
1-3. 他の論文公開手段と比べたJ-STAGEの強みとは
先に述べた「誰もが無料で利用できる」ほかに、J-STAGEは、以下のような強みを持っています。
- 文部科学省所管のJSTが運営しており、信頼性と安定性が高い
- 日本語・英語の論文を掲載でき、国内外の研究者に広くリーチ
- 学術論文だけでなく、研究報告書や技術報告書なども掲載可能
よって、国内の大学が紀要などをオンライン化するにあたっては、J-STAGEを候補とするのがおすすめです。
第2章|大学のJ-STAGE導入メリットとよくある課題
では、大学がJ-STAGEを利用するメリットとは何なのでしょうか。併せて、導入時の現実的な課題についても確認していきましょう。

2-1. 紀要や論文の可視化・保存・アクセス性の向上
大学の紀要や論文は、印刷物や学内Web限定公開が多く、研究成果が外部から発見されにくい状況である場合が多いです。
J-STAGEに登載すると、DOI(Digital Object Identifier=デジタルオブジェクト識別子)の付与により資料の管理が永続的に可能となり、Google Scholarなどにも自動登録されます。
バックナンバーのアーカイブ化も可能で、研究成果を資産として整理・保存するのに優れた基盤となるでしょう。
2-2. 教員・学生の研究成果を社会に届ける新たな選択肢
J-STAGEは教員だけでなく、学生の研究成果発信手段としても注目されています。
多様な成果物を掲載することで教育成果の可視化につながり、学生の意欲向上やキャリア形成に役立ちます。大学としても教育・研究機関としての価値を高める施策ととなります。
2-3. 活用しないことで起こりうる「研究の埋没」リスク
一方、OA化に対応しない場合、次のような状況がリスクとなることも有り得ます。
- 検索エンジン経由で発見されにくい
- 他大学や企業からの引用・参照機会が減少する
- SDGs推進や大学の研究力強化が求められる時代に逆行する
研究結果や論文は、発表から時間を経て評価されることもあります。安定したプラットフォームで継続的に掲載していることには、大きな意義があるといえるでしょう。
2-4. 実際の導入時に立ちはだかる課題とその乗り越え方
とはいえ、いざJ-STAGEを導入しようとしても、実務上の壁に直面することは多くあります。
まず学内体制が未整備である場合、まずは図書館や広報、研究推進部門などの関係者による連携・推進体制の整備が必要です。
実際の掲載作業には、J-STAGEが発表している詳細なマニュアル資料が助けになります。リソース不足であれば、外部の掲載支援サービスの利用も有効な選択肢となるでしょう。
第3章|どう活用する?大学でのJ-STAGE導入・運用ステップ
続いて、具体的にどう進めるか、J-STAGE導入・運用の4つのステップについて解説します。

3-1. 学内での位置づけを決める:どこが主体?誰が管理?
J-STAGE導入にあたって、最初に考えるべきは学内での位置づけと運用主体です。多くの大学では、研究推進部門・図書館・情報システム部門・広報部門などが関わることが多く、これらを横断する推進プロジェクトの設置が効果的です。
特に重要なのは「誰が運用を主導し、どのような体制でフォローするか」です。プロジェクト関係者間で、日常的な掲載作業や問い合わせ対応などの役割とタスクを洗い出し、明確にしておけば、無理のない運用で属人化やトラブルを防げます。
3-2. 掲載に必要な準備とワークフローを把握する
掲載準備として必要なのは、論文データの整備と各種規定の策定です。最低限、論文フォーマット(PDFまたはXML)、投稿規定、著作権同意書の雛形は準備しておきましょう。
J-STAGEの投稿は、管理画面からオンラインで行います。アップロードの流れや注意点は公式マニュアルで確認できるため、着実にステップを踏めば問題ありません。初めての場合は試験的に少数の論文から掲載を始め、運用フローを習得するのが現実的です。
関連記事:【J-STAGE掲載】論文の価値を上げる!登載プロセスから助成金獲得への活用法を解説!
3-3. 限られたリソースでも実現できる、外部支援サービスの活用術
人手や時間が限られている大学にとっては、支援サービスを提供する企業も注目しておきたい存在です。論文データの整形、著作権処理支援、投稿代行などを依頼できます。
J-STAGEの掲載要件に精通した専門事業者の力を借りれば、学内の負担を大きく減らしつつ、短期間での立ち上げが可能となります。特に初年度や新規プロジェクトの立ち上げ時には検討する価値が高いでしょう。
関連記事:【J-STAGE】論文誌を掲載したい学会のための代行サービス基礎情報
3-4. 効果的な運用を継続するための工夫とは
運用が軌道に乗った後は、継続的に研究成果を発信し続ける体制づくりが重要です。
- 定期的な論文募集スケジュールを設定する
- 学内の研究会や発表を掲載対象に加える
- 教職員向けの説明会を実施する
などの工夫が考えられます。
またアクセス解析によって得られるデータは、学内の発信のモチベーション向上や、外部への研究力アピールにもつなげられます。
第4章|活用事例から学ぶ!大学の研究ブランディングとJ-STAGEの可能性
研究力を可視化し、外部評価や資金獲得につなげていくには、単に論文数を増やすだけでなく、その成果をどのように発信していくかが重要です。J-STAGEでは論文の掲載後、すぐにDOIが発行されるため、研究成果の「見える化」および広報にも役立つプラットフォームといえるでしょう。
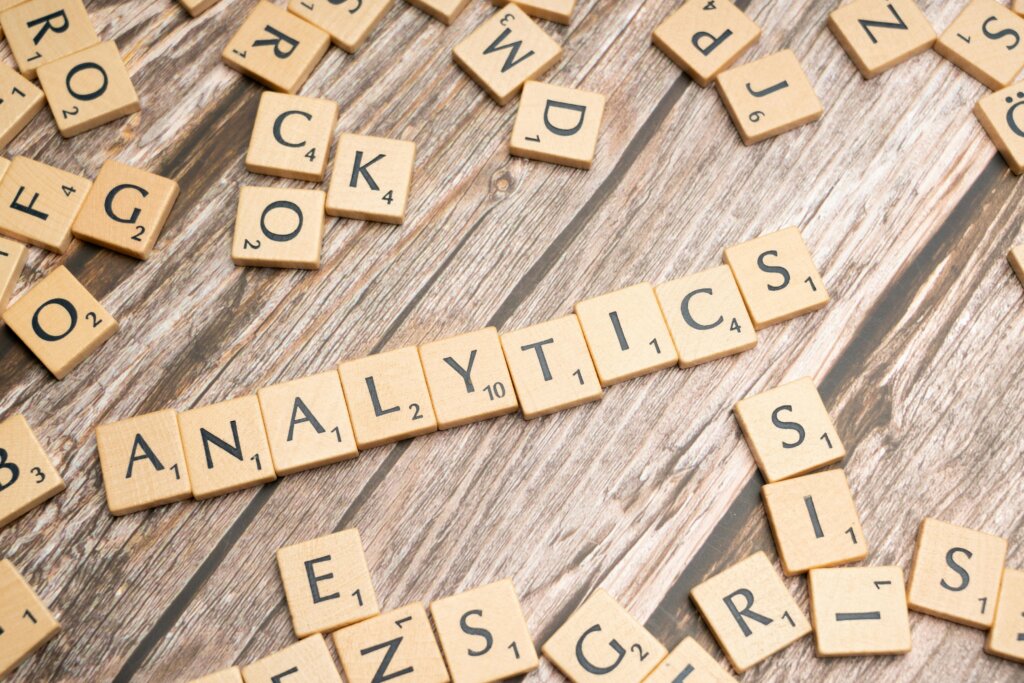
4-1. 信州大学の研究IRレポートへの活用事例
こうした特性を積極的に活かしているのが信州大学です。同大学では2020年から、研究業績を指標とする傾斜配分交付金制度への対応として、J-STAGEから機械的に論文のメタデータを取得。学内のデータベースと照合する取り組みを始めました。
同大学に関連する学術論文のデータ整備を進めて研究IRレポートの作成に役立てた結果、「2年間に発表された約1700の論文データを1日程度で処理できた」と報告しています。
こうして発表された研究IRレポートは、大学としての説明責任や透明性の向上に寄与していると考えられます。
参考記事:「J-STAGE を活用した日本の学術論文データの整備」(『大学評価と IR』第 12 号)久保・伊藤、 2021
4-2.新潟大学による学内OA方針への活用事例
一方、新潟大学付属図書館の2021のセミナー資料によると、J-STAGEは国内論文のOA化推進に不可欠なインフラであり、学内OA方針の実施においても重要な役割を果たしていることが読み取れます。
特に、教員の研究成果の集約先が「ほぼJ-STAGEと医中誌Web」であることが示されています。
参考資料:「オープンアクセスの歩みと新潟大学オープンアクセス方針の策定について」新潟大学付属図書館、2021
4-3.各大学のOA化方針をチェック
研究成果をJ-STAGEで公開することに加え、「どう見せるか」「どう伝えるか」も大学のブランディングには欠かせません。
JPCOAR(オープンアクセスリポジトリ推進協会)のWebサイトでは、大学ごとのOA方針へのリンクを掲載しています。大学がOA化のポリシーを発表するのは、研究発信に積極的である姿勢のあらわれであり、学内外からの信頼を得るのにも有効です。
策定・公開に不安がある場合、まずは既存の公開実績の把握や整理から始めてみると良いでしょう。
参考サイト:オープンアクセスリポジトリ推進協会(JPCOAR)
まとめ:学会だけでなく大学でもJ-STAGEの戦略的活用を
大学にとってJ-STAGEは、研究力を可視化し社会に伝える戦略の1つです。次は、自大学の成果を整理し、世界に向けて発信する体制づくりを始めましょう。
日本印刷出版では自費出版や個人・団体様の出版のサポートをさせていただいています。
定期刊行誌だけでなく、単発での書籍制作を承っておりますので、一度当サイトのお問い合わせフォームからご連絡ください。
下記バナーは、書籍制作に関する詳細となりますので併せてご確認ください。