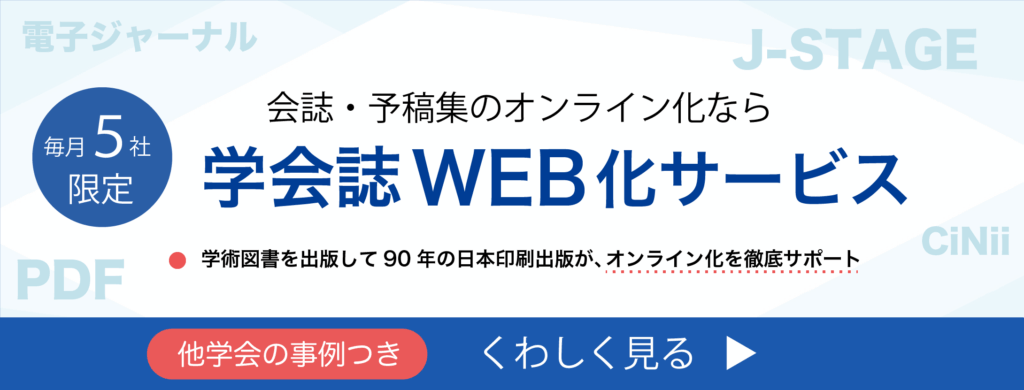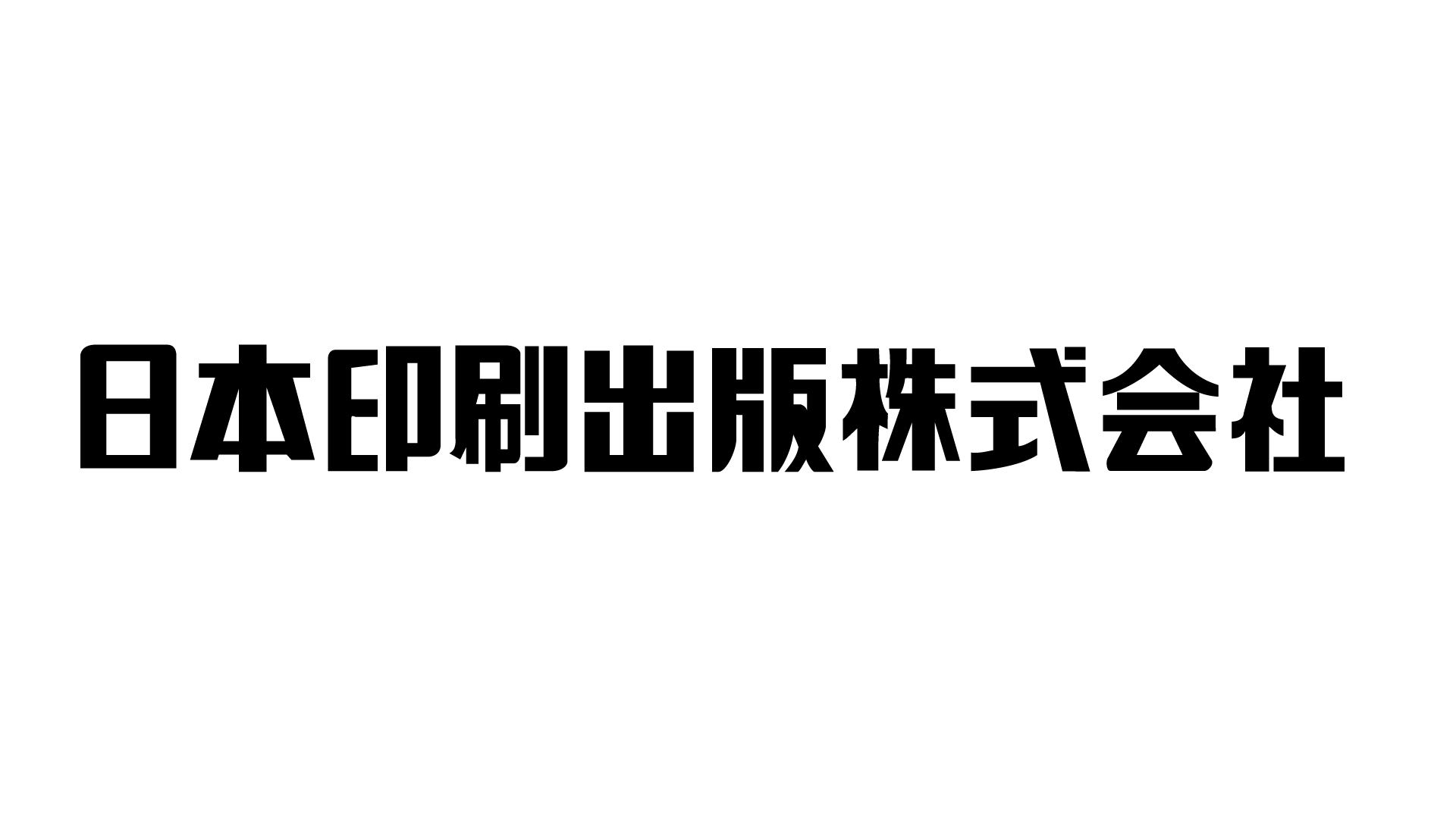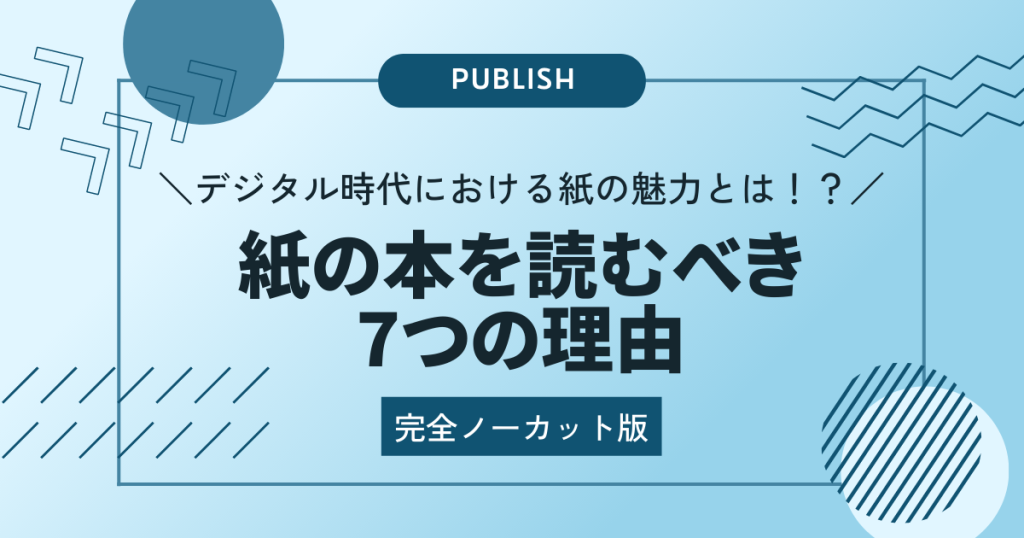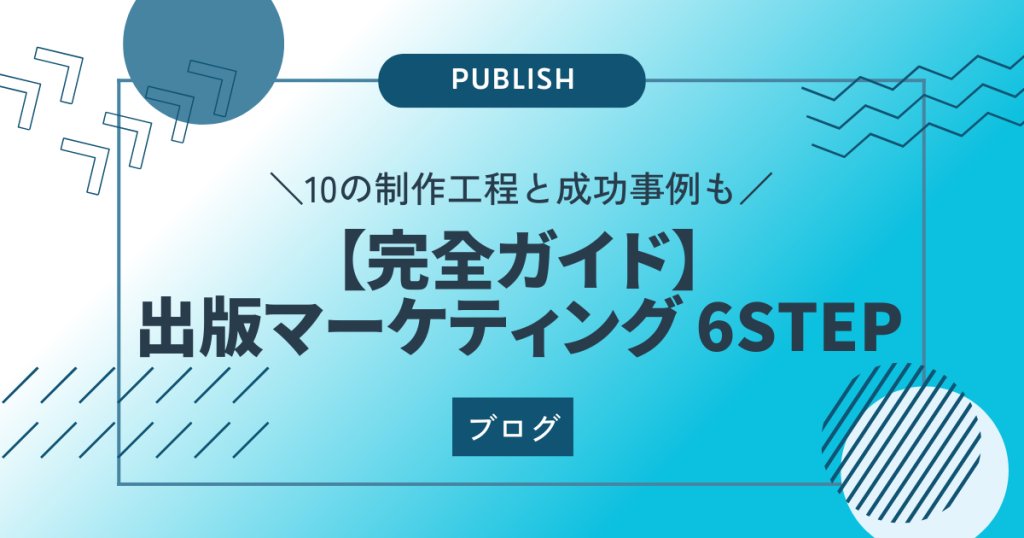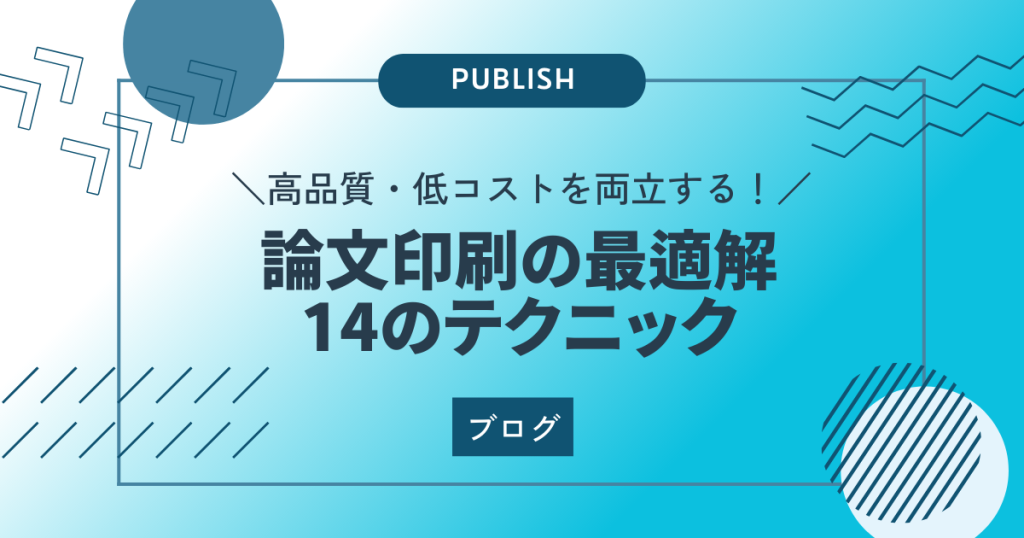「学会誌って第四種郵便物で送れる?」
「第四種郵便物の認定って、どこに申請すればいい?」
そんな疑問を抱える学術誌の編集委員や事務局担当者に向けて、この記事では、学術刊行物として第四種郵便物に認定されるための条件や申請手順について解説します。発送方法、料金体系、注意点までを網羅的にピックアップしました。
郵送コストを抑えつつ、スムーズな学会誌の流通を実現するためのヒントを余すところなくお届けします。
※本文中の説明はすべて2025年4月現在の情報に基づきます。
第1章|第四種郵便物とは? 学術刊行物が対象となる制度の仕組み
まずは「第四種郵便物」制度について、その概要をチェックしておきましょう。
1-1. 第四種郵便物とは? 制度の背景と目的
「第四種郵便物」とは、文化・教育・福祉・学術の発展を促進するため特別な低料金が設定された郵便物です。1947年に制定された郵便法に基づき、「社会的・公共的に価値の高い刊行物や物品の流通を経済的に支援し、公共福祉の増進に寄与すること」を目的としています。
1-2. 第四種郵便物の4分類
第四種郵便物は以下の4種類に分類されています。
- 通信教育用郵便物
- 点字郵便物・特定録音物等郵便物
- 植物種子等郵便物
- 学術刊行物(学会誌・ジャーナルはこれに相当)
1-3. 通常郵便や第三種郵便との違い
第四種郵便物は「通常郵便」や「第三種郵便」とは料金体系・対象物が異なります。また、料金体系は、第四種郵便物のカテゴリによっても変わります。
ちなみに「第三種郵便」は、雑誌を初めとした有料の定期刊行物向けの割引料金制度です。
学術刊行物の料金については、第4章でより詳しく説明します。
第2章|学術刊行物と認定される条件と申請方法【様式51対応】
次に、郵便上の「学術刊行物」に認定されるための条件や、申請方法について説明します。
2-1. 認定を受けるための基本条件(発行主体・回数・内容)
学術刊行物として認定を受ける条件は、「①発行主体が学術研究を目的とする団体」であり、「②年に1回以上定期的に発行」され、「③学術研究の成果や情報が主な内容である」という点です。
また、郵便法の要件に基づき、「特定の政治活動・宗教活動を目的としていない」点も重要です。
これらの条件を満たしていれば、ほとんどの学会誌は認定を受けられます。
2-2. 日本郵便による指定の流れと必要書類
申請は、最寄りの郵便局への問い合わせから始まります。申請書は「様式51」を使用してください。
申請書のほか、刊行物の最新号サンプル2部、定款・寄付行為(学術団体であることを証明できるもの)も携行しましょう。提出後、日本郵便による審査を受けます。
承認されたら、表紙には「承認日付」を印刷する必要があります。印刷・送付の工程も考慮し、余裕をもったスケジュールで申請しましょう。
指定を受けた刊行物は、郵便局のWebサイトでも一覧表で公開されています。
2-3. 【チェックリスト】認定前に確認したい6つのポイント
申請には、以下のチェックリストをぜひ活用してください。
□ 定款・寄付行為(学術団体であることを証明できるもの)があるか
□ 営利目的ではないことが明確か
□ 定期的な発行実績が1年以上あるか
□ 内容は学術的な論文・研究報告が中心か
□ 会員向けの配布が主目的か
□ 過去の発行物サンプルは体裁が整っているか
第3章|学会誌の郵送方法:表記・梱包・郵便局での発送まで
認定を受けたら発送の手続きに入ります。いくつかのルールやコツがあるので、解説していきましょう。
3-1. 「第四種郵便物」送付ルールとサイズ上限
第四種郵便物で学会誌を送付するのであれば、封筒は、所定の箇所が確認できるものを使用します。
サイズ制限は「最長辺60cm・3辺合計90cm」となっています。多くの学会誌が採用しているA4・レターサイズ・B5などであれば、おおむねサイズを気にする必要はないでしょう。
3-2. 中身が見える梱包とは? 見せる箇所と制作時の注意事項
「中身が見える梱包」は郵便局員が内容物を確認できるようにするためのものです。透明フィルム素材の封筒や半透明の封筒、窓付き封筒などが良いでしょう。
表紙に印刷された「承認日付」が視認可能な形で梱包・送付してください。完全密閉の厚紙封筒やテープで完全に封をしてはいけません。
内容物の確認ができる第四種郵便物対応の封筒が市販されているので、そうした商品を利用すれば簡単です。
3-3. 郵便局窓口での提出手順と担当者が気をつけるべきこと
発送時は郵便物を重量・サイズごとに分類し、窓口で「第四種郵便物の発送」と伝えます。
スムーズな発送のため、初回発送時はコピーした認定通知書を持参しましょう。大量発送の場合は事前に連絡しておくと良い場合があります。
重さの区分ごとに分けておく、混雑しない時間帯を選ぶなどの工夫も効果的です。
第4章|学会誌を安く送る!重さ別・第四種郵便物の料金体系【2025年対応】
続いて、どれだけコストを抑えられるのかなど、具体的な料金体系についても説明します。

4-1. 最新の料金体系(2025年版)と重さ別のイメージ
第四種郵便物のうち「学術刊行物郵便物」の料金は、「100g以内37円」で、それ以降、さらに「100gごとに+26円」となります。上限は「1kg以内」です。
例えば、一般的な書籍の重さを基準にすると、以下のような料金イメージとなります。
- 150g(文庫本程度) 63円
- 300g(単行本程度) 89円
- 700g(雑誌程度) 193円
※料金は2025年4月現在のものです。
4-2. 第三種郵便との比較
ちなみに「1-3」で述べた通り、第三種郵便は一般的な定期刊行物(年4回以上の発行・有料販売)を対象とした、雑誌や新聞向けの制度です。こちらも広告比率など、一定の認定基準があります。
送料は第三種よりも第四種の方がさらに安く設定されています。
4-3. ゆうメール・第三種郵便とのコスト比較と使い分け
郵便局の一般向けサービスである「ゆうメール」についても触れておきましょう。
220gの冊子を例にすると、第四種郵便物は63円、第三種郵便は95円、ゆうメールは215円、定形外(普通)郵便は320円です。
状況に応じた使い分けとして、
- 認定済みの定期発行物には「第四種郵便物」
- 臨時発行物や認定外の出版物には「ゆうメール」
- 急ぎ(速達)や少部数の場合は「定形外郵便」
という選択肢が考えられます。
また、民間の宅配業者によるメール便サービスもあるのでそちらもチェックしてみてください。
外部リンク:ヤマト運輸「ネコポス」、佐川急便「飛脚メール便」
4-4. さらなる発送コスト削減と情報発信力強化を両立するには
さらに学会誌発行のコスト削減を目指す方法があります。冊子体とオンライン版の併用、すなわち「ハイブリッド出版」を検討してみてはいかがでしょうか。
J-STAGEを活用した学会誌のオープンアクセス化には、アクセスの多様性確保、検索可能性の向上、国際的な可視性の強化、アーカイブ機能の充実、長期的なコスト削減などのメリットがあります。
第四種郵便物を活用しながらオンライン移行も進めれば、コスト効率と情報発信力の両立が可能です。
第5章|ToDoリスト:次号の発送に間に合わせる申請ステップ
最後に、次回発行号から第四種郵便物として送付可能にするために必要なタスクを、ToDoリストに整理しました。ぜひ活用してください。
□Step 1(発行予定日の3カ月前まで)
・郵便局に問い合わせ、最新の申請要件を確認
・学会理事会や編集委員会での承認を得る
□Step 2(発行予定日の2カ月前まで)
・申請書類一式を準備し郵便局に提出
□Step 3(認定後)
・対応封筒の準備
・発送手順の確認・必要であれば提出局へ連絡
まとめ:第四種郵便物認定を受けて学会運営を効率化しよう
学会誌・学術雑誌の第四種郵便物申請は、余裕をもったスケジュールで進行するのが成功の秘訣です。制度を正しく理解して、学会運営の効率化と会員サービスの向上を目指しましょう。
日本印刷出版では自費出版や個人・団体様の出版のサポートをさせていただいています。
定期刊行誌だけでなく、単発での書籍制作を承っておりますので、一度当サイトのお問い合わせフォームからご連絡ください。
下記バナーは、書籍制作に関する詳細となりますので併せてご確認ください。