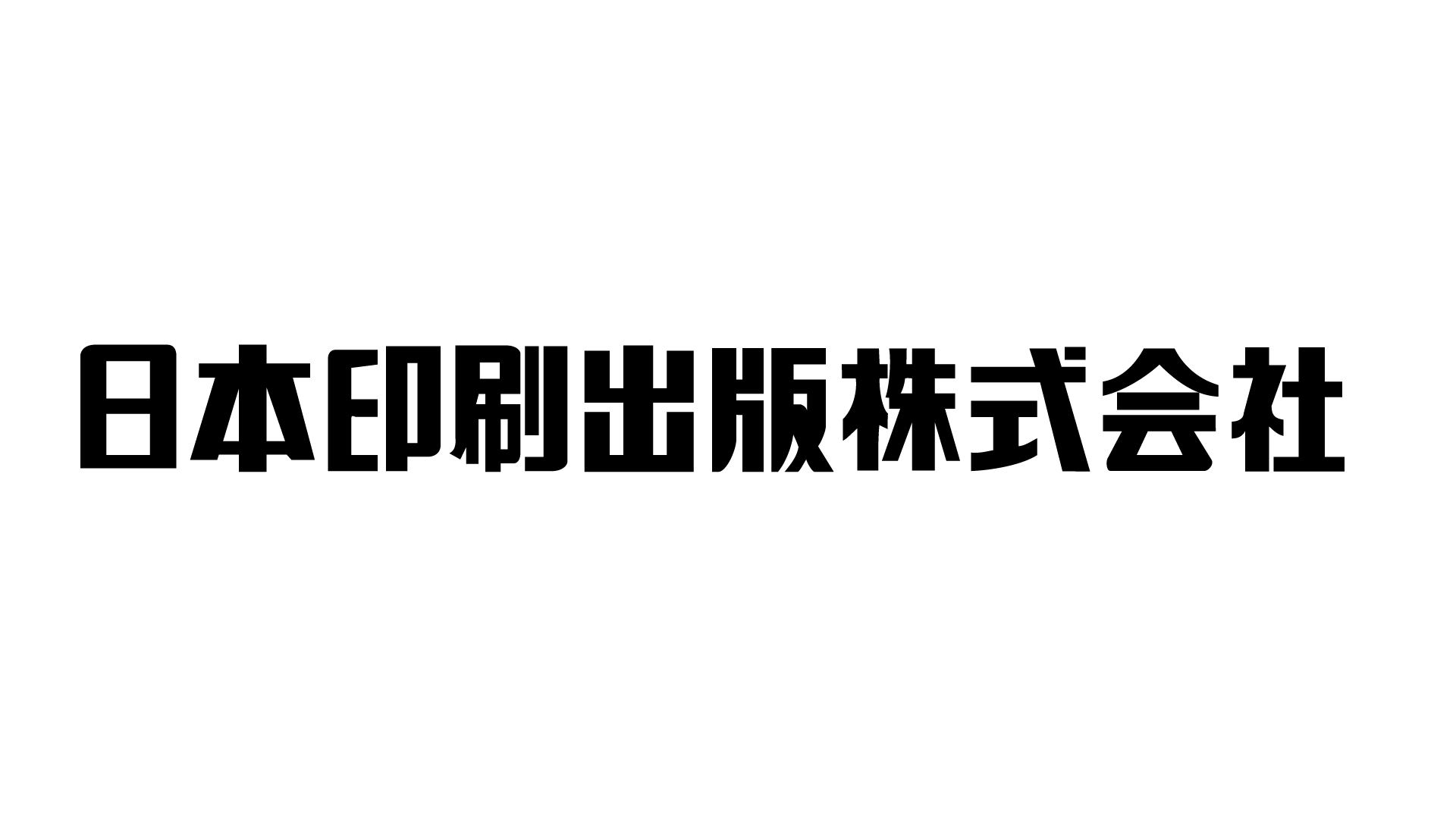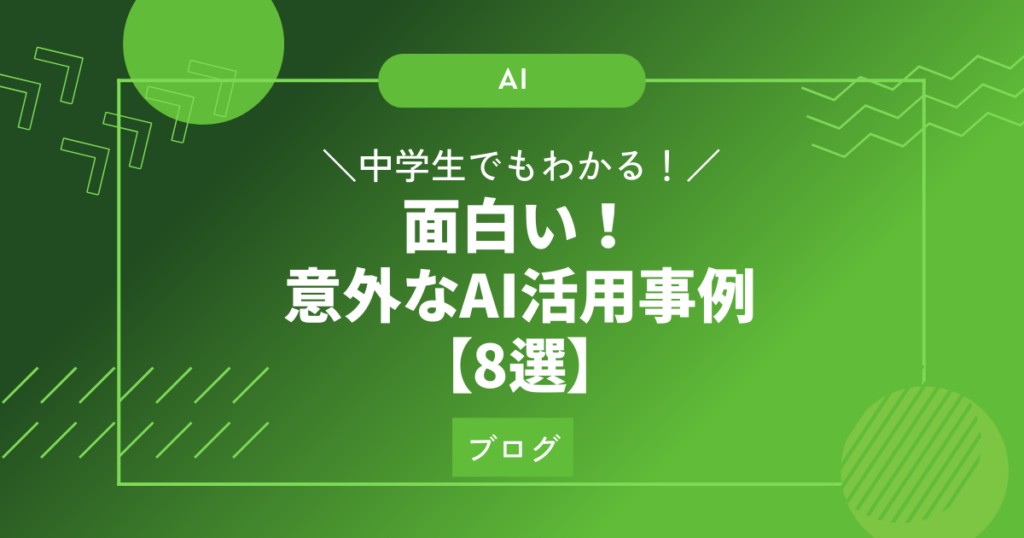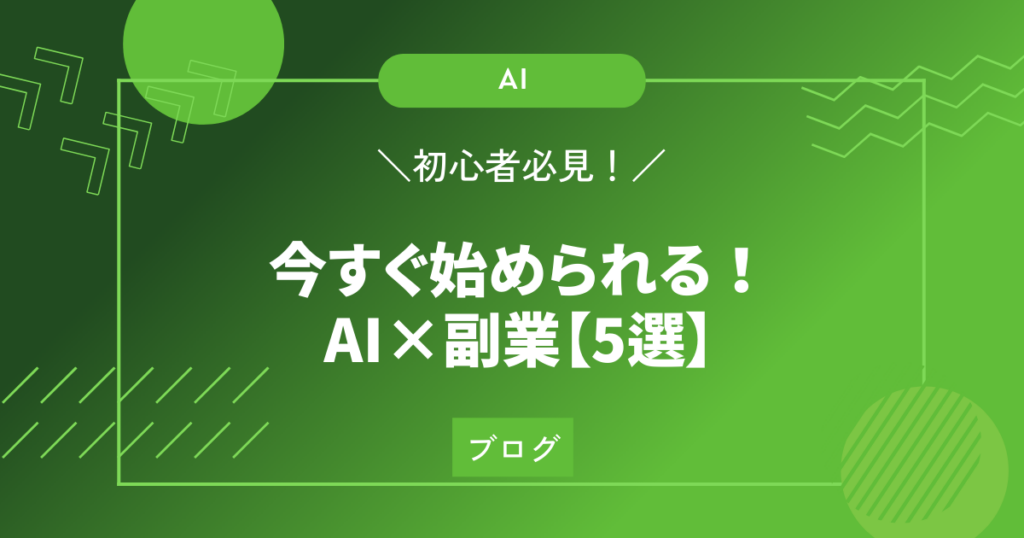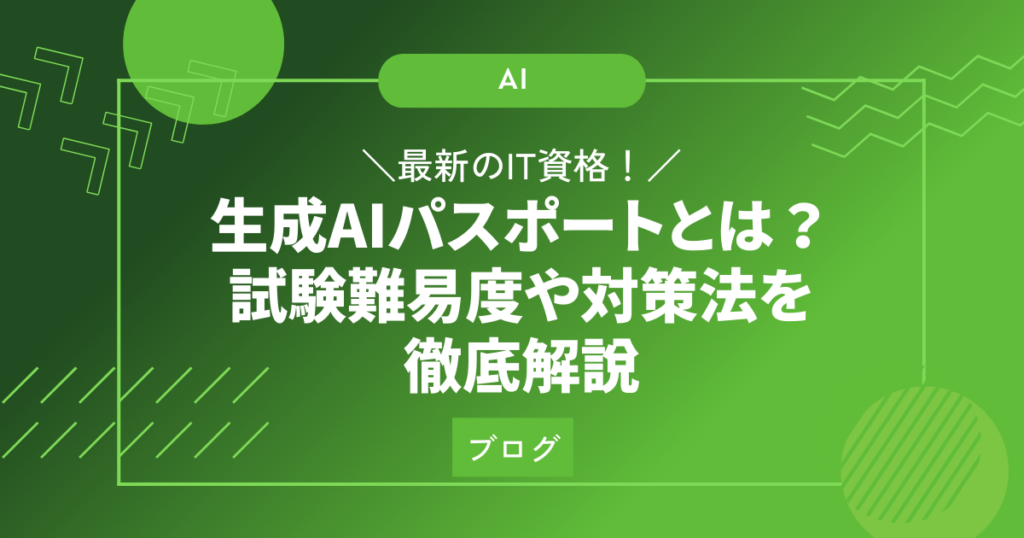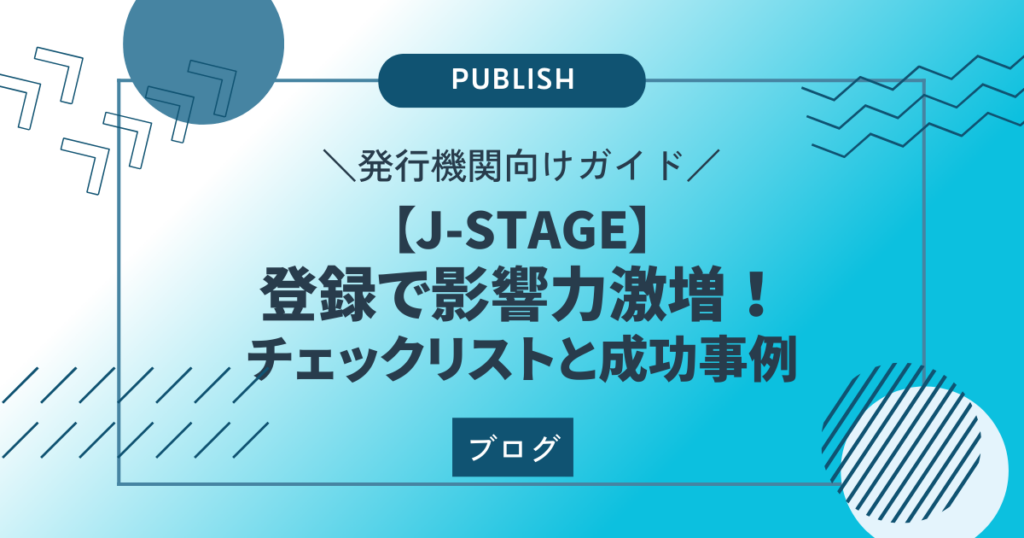
「新規登載の登録申請の具体的な流れや、準備すべき書類を詳しく知りたい」
「学会誌の投稿規程や査読プロセスの整備に関するガイドラインや事例はある?」
J-STAGEは、学術誌や学会誌をオンラインで公開し、研究成果を広く発信できるプラットフォームです。本記事では、J-STAGEの登録要件や申請手順、審査のポイントを詳しく解説します。さらに、ジャーナルの電子化による成功事例や運用のコツ、よくある質問にも対応。ジャーナルの電子化を検討しているなら、ぜひ参考にしてください。
※本文中の説明はすべて2025年3月現在の情報に基づきます。
目次
Toggle1. J-STAGEに登録する前に学会・ジャーナル発行機関が知っておくべきポイント
まずは新規登録にあたっての審査条件など、基礎事項を押さえておきましょう。
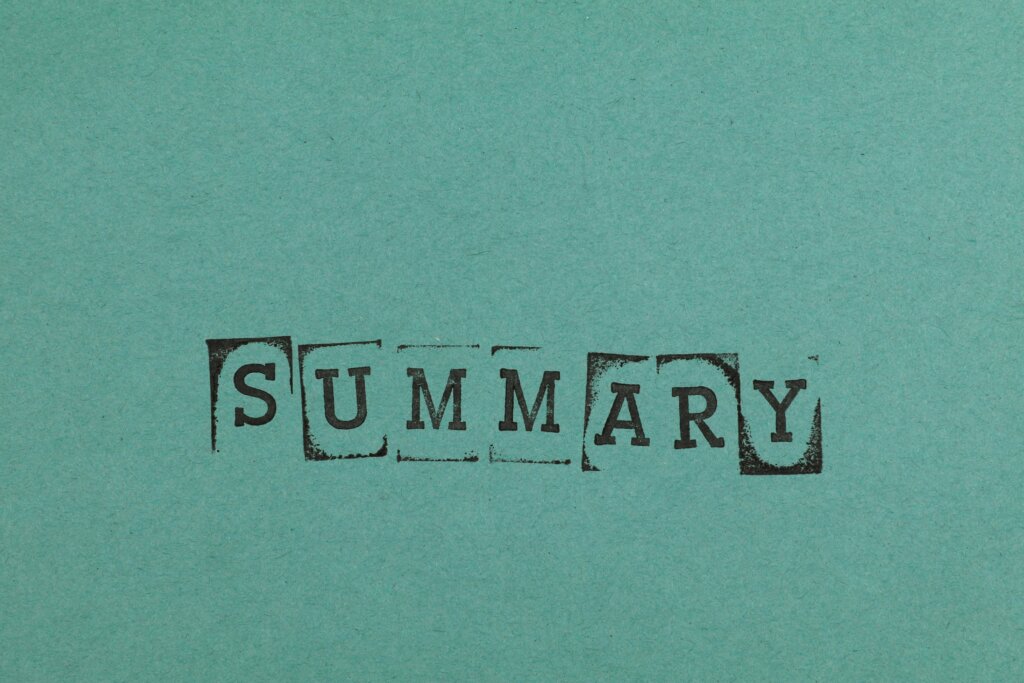
1-1. 公開先としてJ-STAGEを活用するのに必要な最低限の要件とは?
J-STAGEへの論文登録には、学術雑誌や学会誌を発行する機関による手続きが必須です。営利目的の企業や、研究者個人での登録は認められていません。
また、利用申し込み後には審査があります。定期的な刊行、学会活動の実態、すでに公開されている記事と重複しないかなどが審査基準です。論文査読のように、研究内容を評価するものではありません。詳しくは、J-STAGEの「登載ガイドライン」をチェックしておきましょう。
あわせて読む:【J-STAGEとは】論文・電子ジャーナル公開前に発行機関が知るべき6項目
外部リンク:J-STAGE「登載ガイドライン・マニュアル>推奨基準」
1-2. 利用申請前に準備すべき必要書類・資料
J-STAGEの登録には、学術雑誌の概要のほか、発行機関の運営体制、投稿規程などの情報が必要です。事前に整理し資料化しておくと申請がスムーズになります。
サービスの利用開始後には、管理画面から記事データを登録します。XML形式またはPDF形式が標準です。データの準備には外部の掲載代行サービスを活用すると、手間が省けるでしょう。
あわせて読む:【初心者向け】J-STAGEの論文XMLとは? 基本フロー&ツール比較、作成効率化のヒントも
1-3. 電子化・オープンアクセスのプロジェクト化を推奨
電子化およびオープンアクセス化にあたっては、編集体制や投稿規程を見直さなければならない場合が多いです。
従来の進行のままでただ登載申請をするのではなく、申請完了を最初のゴールにしてこれらの項目を洗い出し、1つのプロジェクトとして取り組んでいくのがおすすめです。
1-4. J-STAGEに登録すべきか迷ったら? 発行機関向けチェックリスト
J-STAGEへの登録が本当に必要かどうか、以下のチェックリストを活用して判断しましょう。
☑ 閲覧数・引用数を増やして学会の価値や認知度を高めたい
☑ バックナンバーの電子化により管理コストを削減したい
☑ 研究助成機関の要件に対応したい
☑ 今後の学会運営やジャーナルの編集に、データを有効活用したい
☑ 電子ジャーナルと従来の冊子体の併用で、多様な会員ニーズに応えたい
1つでも当てはまるのであれば、ぜひJ-STAGE導入に動きましょう。
2. J-STAGEの学会誌登録手順:スムーズに申請を進める方法
続いて、実際に申請を進める手順を解説します。

2-1. J-STAGE登録の基本フローと申請方法
J-STAGEへの登録にはまず、J-STAGEサービス利用申込ページからサービス利用申込書をダウンロードし、必要事項を記入します。
利用申し込みは基本的にオンラインで可能です。ただし並行して郵送での見本誌の提出が必要です。
審査が通れば、論文データを登録する「編集登載システム」が利用可能になります。
2-2. 申請時に提出する書類とその記入方法
申請に必要な書類は以下の通りです。先に紹介した利用申込ページでは、各項目の記入例の資料も公開されていますのでよくチェックしてみてください。
- サービス利用申込書(全発行機関共通:エクセル)
- 投稿規程(投稿ありの雑誌のみ:PDF)
- 査読規程・体制(査読誌の場合のみ:PDF)
- 発刊計画(未刊行の場合のみ:PDF)
また、ISSNの取得が必要な場合は、申請前に取得しておくとスムーズです。
2-3. 審査の流れと承認までにかかる期間
J-STAGEの審査には通常1〜2カ月程度ほどかかります。不備や記入漏れによる差し戻しなどの対応も想定し、余裕をもって提出しましょう。審査結果はJ-STAGEから担当者宛てにメールで通知されます。
2-4. J-STAGE登録後にすぐ行うべき初期設定
登録後は、記事データのアップロードを行いましょう。最新刊の記事を1年間は会員限定公開にするなど、戦略的に公開スケジュールを調整すれば、会員の満足度を確保しつつ読者の関心を引きやすくなります。
また、メタデータの設定も重要です。より多くの人に読まれるよう、検索者の意図も考慮して、関連キーワードを登録してください。
3.J-STAGEの活用で効率化を実現した学会の実例
ここで、実際にJ-STAGEの活用で効果を上げた学会の事例を1つ紹介しましょう(※画像はイメージです。紹介する団体とは関係ありません)。

3-1. 「日本繁殖生物学会」がJ-STAGEを導入した目的
日本繁殖生物学会は、1955年から『Journal of Reproduction and Development (JRD)』 を発行しています。53巻目を迎える2006年、J-STAGEを導入しました。
特にオンライン投稿・査読システムを活用し、編集作業の効率化と査読期間の短縮することを重視していました。
3-2. 具体的な施策内容と効果
さらに同学会は「CrossCheck機能」(現在は「類似性チェックサービス」として提供)を利用し、剽窃チェックも徹底。総合的な論文の品質向上を図りました。
J-STAGEでの公開後、特に海外からの投稿数が飛躍的に増加しました。当時の担当者は、「新しい投稿審査システムにより査読期間が短縮され、査読者の選定も容易になった」と明らかにしています。
J-STAGEを通じて学会誌の国際的な評価が向上し、J-STAGEの有用性が改めて認識されることなった事例です。
参考:「J-STAGE NEWS NO33」(2012年、科学技術振興機構)
4. J-STAGEの登録に関するよくある質問と回答(FAQ)
最後に、初めてJ-STAGEへ登録するにあたり、学会やジャーナル発行機関が抱く疑問とその回答をまとめました。

4-1. J-STAGEの登録費用や維持費はどのくらい?
J-STAGEへの論文掲載・利用は、基本的に無料です。一部のオプション機能を使用するのに追加費用がかかります。
外部の掲載代行サービスを利用する場合は、どのような作業を任せられるかなどを相談し、料金を問い合わせてみましょう。
あわせて読む:【J-STAGE】論文掲載に料金はかかる? 公開手順や注意点も解説
4-2. 登録後、論文の掲載作業はどのように進めればよいか?
論文のアップロードやメタデータの入力は発行機関側で行います。登録後すぐに着手できるよう、編集担当者と入力担当者などの体制・役割を決めておきましょう。公式の『編集登載マニュアル』で、アップロード手順を確認しておくとスムーズです。
あわせて読む:【編集登載】J-STAGEマニュアル中学生にもわかる簡単8ステップ!
4-3. 掲載後に誤りが見つかった場合、エラータを発行できるか?
既に公開した論文に誤りがあった場合、J-STAGEでエラータ(訂正記事)を掲載できます。
あわせて読む:【論文の訂正方法】J-STAGEのエラータ記事とは 修正・撤回時の手順や注意点
4-4. 論文のアップロード作業や運営で困ったときのサポート窓口は?
J-STAGEには登載機関専用の問い合わせ窓口があり、質問等をメールで受け付けています。ただし公式サイトにはマニュアルやFAQが豊富に公開されており、それらで解決できることも多いです。
技術面や運営体制で不安がある場合は、掲載代行サポートを活用するのがおすすめです。
まとめ:J-STAGEへ登録し学会誌・ジャーナルの価値を最大化
J-STAGEへの登録は、論文の可視性を高め、国際的な評価を得るための重要なステップです。本記事のチェックリストや実例を参考に、スムーズな登録と効果的な運用を実現しましょう。
日本印刷出版では、J-STAGE掲載に関するご相談をお受けしております。
・J-STAGEを活用したいけど、何から始めればいいかわからない
・自分達にあったJ-STAGEの活用方法を知りたい
どんなお悩みでも、お気軽にご相談ください。